要約
リスクコミュニケーションのためのリスク評価はマクロなアプローチ(詳細ではないがさまざまな種類のリスクを俯瞰的に眺める)のほうが望ましいと考えます。マクロなアプローチの化学物質のリスクへの適用として、実際の農薬の残留基準値超過事例を用いて計算します。
本文:リスクコミュニケーションのためのリスク評価
本ブログではこれまでに、「食品安全に係る施策を進める上でリスクコミュニケーションがボトルネックになってきた」ということを書いてきています。安全性そのものよりも社会の受容性の問題によって、物事が進まなくなってきているのです。

この記事では、原発処理水の放出について例を出していますが、このほかにも、米の低カドミウム品種の導入においても、この問題で大きくつまずいてしまいました。放射線育種という長年使われている技術が突如として危険視されてしまったのです。

新型コロナウイルスが発生した際が顕著でしたが、新たなリスクの社会問題が発生するたびに、リスクコミュニケーション(リスコミ)の重要性が叫ばれます。ところが、喉元過ぎると忘れ去られてしまい、次の問題が起こった際にまたゼロからのスタートとなるのです。
さて、冒頭に紹介した過去記事では、リスコミがボトルネックとなって物事が進まない時代においては、リスク評価・リスク管理の方法もリスコミしやすい方法に考える必要がある、ということも書きました。
今までの方法がダメというよりも、規制のためのリスク評価(これまでの方法)とリスコミのためのリスク評価は分けるべきなのです。
リスコミに適したリスク評価とは、個別の要素を細かく評価するミクロなアプローチではなく、ざっくりと全体を俯瞰するマクロなアプローチです。
全体を俯瞰するマクロなアプローチは、
・定量的
・他のリスクと比較可能
・安全側に偏らない
・判断の目安となるものさしをつける
などの特徴があります。
化学物質に関してはこのマクロなアプローチで扱うのがなかなか難しかったのですが、本ブログの中でもいろいろと試行錯誤してきた結果、だいぶ扱い方がわかってきました。
本記事では、過去に記事化した農薬の残留基準値超過事例を用いて、どのようにマクロなアプローチで扱うのかについてまとめます。まずはリスク評価のミクロとマクロのアプローチの違いについて再整理し、次に実際に以下の「180倍の農薬、食べると嘔吐や失禁」などと取り上げられてしまった事例で計算してみます。最後に、マクロなアプローチの活用について考えてみましょう。

リスク評価のミクロとマクロ
リスコミに適したリスク評価とは、個別の要素を細かく評価するミクロなアプローチではなく、ざっくりと全体を俯瞰するマクロなアプローチである、と書きましたが、もう少し詳しく説明してみましょう。
ミクロなアプローチ
個別のリスク要因を対象に詳細にリスクを評価する
->個別のリスク要因について「安全か否か」を示す
マクロなアプローチ
詳細ではないがさまざまな種類のリスクを俯瞰的に眺める
->本当に避けるべきものは何かを示す
ミクロなアプローチでは農薬や添加物、プラスチックやPFASなどが注目されます。これらについて、調べれば調べるほどにハザード(大量に曝露した際にどのような影響が現れるか)についての情報がたくさん集まります。このような情報に触れれば触れるほどに、その影響が心配になってきます。
その結果、以下のような思考が生まれてきてしまうのですね。
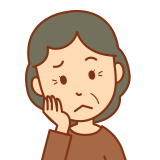
農薬や添加物を避けて、ペットボトルをやめて、テフロンのフライパンもやめれば安全になるのね?
そこで、いくら「ADI(許容一日摂取量)というものがあって、それ以下になるよう管理されていて、、、」という説明をいくらしても、なかなか響かないのは多くの人が感じているところではないでしょうか?
個別のリスクについて深掘りするよりも、もっと全体を見て、効果の高い対策から手をつけましょう、というほうがわかりやすいと考えます。そこで、マクロなアプローチが必要になってくるのです。
ただし、化学物質の場合は物質によってバラバラで、死亡率などの統一的な指標で評価することが困難です。通常、死亡に至るもっと手前のエンドポイント(体重減少など)で評価するため、定量化が難しかったのです。
発がんに関してはまだ定量化がやりやすいので、いろいろ本ブログでも試行錯誤してきました。これらの結果は以下の記事などを見てください。

リスクの定量化のものさし
取り上げる事例は、冒頭で紹介した過去記事で取り上げた、イソキサチオンという農薬が残留基準値を超えて検出された事例です。
市によると、イソキサチオンの基準値は0・05ppmだが、検査で9ppmを検出。生産者は特定している。体重60キロの人が20グラムを食べると、よだれが垂れる、嘔吐(おうと)や失禁を引き起こすなどの症状が出ることがあるという。
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/671685/
以下の報告を見ると、残留濃度の確定値としては8.4ppm(mg/kg)でした。イソキサチオン以外にも、アラクロール(検出値:0.03ppm、基準値:0.01ppm)とテフルベンズロン(検出値:0.85ppm、基準値:0.01ppm)が基準値を越えて検出されたとのことです。
さて、ここまでの情報を用いてリスク評価を行います。方法はすでに過去記事で書いた「動物実験の結果から化学物質の死亡リスク、損失余命、DALYを求める方法」と使いましょう。

イソキサチオンのADIは0.002mg/kg体重/日です。これは以下の記事にてリストを作っていますので、他の農薬についても調べることができます。

イソキサチオンのADI = 0.002 mg/kg体重/日
↓100倍
NOAEL(無影響量) = 0.2 mg/kg体重/日
↓5倍
死亡率のNOAEL = 1 mg/kg体重/日
↓
これを5%の影響率(=死亡率)とみなす
次に1日に春菊を食べる平均的な量が必要になります。
これは、令和5年国民健康・栄養調査の結果から、表5-1「食品群別摂取量 – 食品群、年齢階級別、平均値、標準偏差、中央値 – 総数、1歳以上」を使います。

簡単な分類ではありますが、これくらいで十分でしょう。春菊というカテゴリはありませんが、「その他の緑黄色野菜」の年齢総数の平均値である31.7g/日を使います。
体重50kgの人の曝露量(mg/kg体重/日)は
残留濃度(mg/kg)×食品摂取量(g/日)/1000(g/kg)/50(kg体重)
= 8.4×31.7/1000/50
= 0.00533 (mg/kg体重/日)
曝露量1 mg/kg体重/日のとき、5%の死亡率
曝露量0.00533 mg/kg体重/日のとき、x%の死亡率
という比例計算をすれば、
x = 0.05×0.00533/1 = 0.0002665
となり、これを年あたりに変換するために70で割ると、
0.0002665/70 = 0.0000038
となります。
つまり、10万人あたりの年間死者数は0.38人となります。
これを回帰式を用いて損失余命やDALYに変換すると、
損失余命 = 18.082×0.38^0.9432 = 7.3
DALY = 19.684×0.38^0.9574 = 7.8
となりました。
これをリスクのものさしで表現すると以下のようになります。
| 原因 | 死亡率 | 損失余命 | DALY |
| がん | 346 | 5722 | 6025 |
| 自殺 | 18 | 643 | 660 |
| 交通事故 | 3.8 | 108.7 | 204.6 |
| 火災 | 1.2 | 23.0 | 90.3 |
| イソキサチオンが8.4ppm残留したその他の緑黄色野菜を毎日31.7g一生涯食べ続ける | 0.38 | 7.27 | 7.80 |
| 自然の力への曝露 | 0.12 | 2.83 | 4.66 |
マクロなアプローチをどのように活用していくか?
さて、イソキサチオン以外にも、アラクロール(検出値:0.03ppm、基準値:0.01ppm)とテフルベンズロン(検出値:0.85ppm、基準値:0.01ppm)も基準値を超えて検出されているため、この二つについても同様に計算してみましょう。それぞれ、アラクロールのADIは0.01mg/kg体重/日、テフルベンズロンのADIは0.021mg/kg体重/日ですので、この情報がわかれば同じように計算できます。
| 原因 | 死亡率 | 損失余命 | DALY |
| がん | 346 | 5722 | 6025 |
| 自殺 | 18 | 643 | 660 |
| 交通事故 | 3.8 | 108.7 | 204.6 |
| 火災 | 1.2 | 23.0 | 90.3 |
| イソキサチオンが8.4ppm残留したその他の緑黄色野菜を毎日31.7g一生涯食べ続ける | 0.38 | 7.27 | 7.80 |
| 自然の力への曝露 | 0.12 | 2.83 | 4.66 |
| テフルベンズロンが0.85ppm残留したその他の緑黄色野菜を毎日31.7g一生涯食べ続ける | 0.004 | 0.091 | 0.092 |
| アラクロールが0.03ppm残留したその他の緑黄色野菜を毎日31.7g一生涯食べ続ける | 0.0003 | 0.0078 | 0.0076 |
イソキサチオンの例に比べると数桁以上もリスクが低いことがわかります。基準値超過の事例の多くはアラクロールくらいのリスクレベルであることが多いです。
さらに、これまで計算されてきたような曝露マージンやどのくらい食べ続ければADIを超えるかという計算も併せて示してみましょう。
イソキサチオンの事例
曝露マージン:38
体重50kgの人が毎日0.012kg一生涯食べ続けるとADIを超過する
アラクロールの事例
曝露マージン:53000
体重50kgの人が毎日17kg一生涯食べ続けるとADIを超過する
テフルベンズロンの事例
曝露マージン:3900
体重50kgの人が毎日1.2kg一生涯食べ続けるとADIを超過する
こんな感じになりました。このように、いくつかのリスクの表現方法の余地を残しておくのもよいでしょう。
なぜ、基準値を超過しているのに、リスクとしてそれほど大きい数字にならないのでしょうか?農薬の基準値は健康影響に関する基準値ではない、ということが一番の理由です。これについては本ブログの過去記事に詳しく書いていますので、そちらを参照してください。

今回、リスクの計算については慢性影響に関するNOAELを使用しました(ADI×100で逆算)が、本来基準値超過は一時的なものなので、急性影響を考慮したほうがよいのでは?という意見もあることでしょう。
ただし、マクロなアプローチのリスク評価においては、細かいことを詰めるよりもざっくりでよいので全体像を示すことが重要です。これはあくまでずっと食べ続けた場合の話、という前提の説明が必要となります。もっとも、イソキサチオンのようなかなりひどい事故事例であっても、一回食べた程度でどうにかなるものではないことは冒頭で紹介した過去記事でも書いています。
さて、最後になりますが、今回紹介した計算も自分でやろうとすると大変です。計算も自動で行えるツールがあったら便利ではないでしょうか?そんなツールについては次回にまた紹介できればと思います。
まとめ:リスクコミュニケーションのためのリスク評価
規制のためのリスク評価とリスクコミュニケーションのためのリスク評価は分けるべきであり、リスクコミュニケーションのためのリスク評価とは、個別の要素を細かく評価するミクロなアプローチではなく、ざっくりと全体を俯瞰するマクロなアプローチです。農薬の残留基準値超過事例を用いて、実際に死亡率や損失余命、DALYをざっくりと計算して、リスクのものさしで表現しました。



コメント