 リスク比較
リスク比較 食品関係のリスクを俯瞰する試み:農薬やPFASなどの位置づけはどの辺か?
食品によるリスクの全体像はどのようなもので、どの要因がどのくらい大きいのか?という全体を俯瞰するマクロなアプローチが不足しています。そこで、世界疾病負荷研究のデータを用いて食品関係のリスクを俯瞰します。農薬やPFASなど話題の化学物質の位置付けも併せて示します。
 リスク比較
リスク比較  化学物質
化学物質  化学物質
化学物質 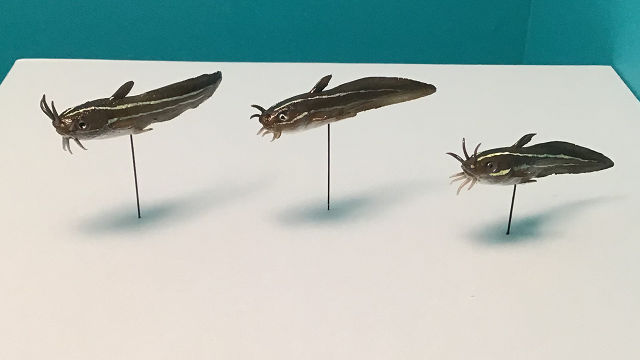 化学物質
化学物質  化学物質
化学物質  化学物質
化学物質  化学物質
化学物質  化学物質
化学物質  化学物質
化学物質  化学物質
化学物質