要約
農薬の発がん性は科学的に完全な白黒がつくものではないため、発がん性あるなしの禅問答は尽きません。その禅問答から抜け出すには、発がん性があると仮定してそのリスクを計算することが有用です。除草剤グリホサートを例に発がんリスクを計算する方法を解説します。
本文:グリホサートの発がんリスクの大きさ
除草剤グリホサート(商品名ラウンドアップなど)の健康影響の第3回になります。第1回の記事では尿中から検出されたグリホサートのリスク評価について解説し、第2回では発がん性の根拠とされた論文を例に疫学調査はなぜ難しいのかを解説しました。


疫学研究の難しさは農薬の曝露量の推定と個別農薬の影響を見ることにあります。信頼性の高い疫学研究に基づくと、グリホサートの発がん性は見られませんでした。
ただし、科学は「ない」ことの証明はできないため(悪魔の証明と呼ばれる)、これからも「発がん性ある派」と「発がん性ない派」の対立や分断は続くことでしょう。
「発がん性ある派」は「発がん性あり=危険=禁止すべき」がロジックとなっており、発がんリスクの大きさをロジックとすることはありません。IARCが評価しているのも「発がん性ありとする根拠がどれくらいあるか」であって、「発がんリスクの大きさがどれくらいか」ではありません。
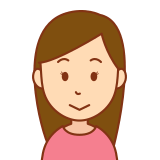
じゃあ実際の発がんリスクの大きさってどれくらいなの??
「発がん性ある派」の人でもこのような疑問を持つと思います。ところが、全然そのような数字を見かけることがないのです。そこで今回は、もしグリホサートに発がん性があったとしたら、そのリスクはどれくらいになるのかを計算してみることにします。
まず、発がん性ありなしの論争は不毛であることを解説し、次に発がんリスクの計算に必要な情報の収集、最後に発がんリスクの計算結果を示します。
発がん性ありなしの論争は禅問答
まず、農薬の安全性審査においてなぜ発がん性の有無が重要かという話から始めます。発がん性があり、さらに遺伝子損傷性(遺伝毒性あり)がある化学物質は、これ以下なら発がんしないという閾値が存在せず、どれだけ曝露量が低くても発がんの確率がゼロにならないとみなします。
この場合、許容一日摂取量(Acceptable Daily Intake, ADI)を設定できないため、農薬として使用できなくなります。ADIは通常、動物実験における無影響用量を不確実係数100で割ることで決定されますが、遺伝毒性ありの発がん物質はメカニズム的に無影響用量が設定できないのです。
このため、農薬の有害性評価を行う食品安全委員会は発がん性の有無に決着をつける必要があります。しかしながら冒頭にも書いたように、科学は「ない」ことの証明はできません。現状、国際的に標準化された試験ガイドラインに基づいた試験をクリアしたものを「発がん性がないということにしましょう」という専門家間の合意によって決まっているのです。
一方で、ヒトの疫学研究を重視する人たちから見ればこれでは不満となり、対立や分断が生まれます。結局のところ、発がん性があるかないかという二者択一の問いは禅問答であり、もめる原因にしかなりません。
科学は白黒つけるための道具ではないのですが、それでも制度上二者択一が求められている、という難しい状況なのです。黒ならその農薬は使用できなくなることがわかっている状況で、専門家に白黒を判断させることが心理的バイアスを生むかもしれません。そして最終的に「科学的に決めました」という決めゼリフで納得を強いるのです。
同様のことが原子力発電所の審査でもあります。原子力発電所の敷地内に「活断層があるかないか」という不確実性の高い問いに対して専門家に白黒つけさせています。専門家なら白黒ハッキリつけられるはず、という世の中の誤解もなかなかなくなりません。
実のところ、遺伝毒性ありの発がん物質であったとしても、リスク評価を行い「十分に低く、受け入れられるリスクレベル」をADIとみなし、残留基準を設定したりすることは本来は可能なはずなのです。
(発がん物質に対する受け入れられるリスクレベルの話は次回に解説しようと思います)
最近のリスク評価では、むしろ発がん物質と非発がん物質を完全に切り離して評価することはもう時代遅れになっています。なぜなら、発がん物質を禁止して非発がん物質に切り替えることで、本当にリスクが減っているのかどうかわからないからです。この場合、発がん物質も非発がん物質も同じ尺度でリスクを比較して判断する必要があるのです。
グリホサートの発がんリスクの計算に必要な情報
では次に発がんリスクの計算に必要な情報を集めましょう。基本となるのは食品安全委員会の評価書です。悪性リンパ腫(非ホジキンリンパ腫もこの中に含まれる)の発生率に関しては唯一以下の記述が見つかりました。
評価書p5-22
(3)18 か月間発がん性試験(マウス)
ICR マウス(一群雌雄各51匹)を用いた混餌(グリホサート原体:0、500、1,500 及び5,000ppm、平均検体摂取量は表18参照)投与による18か月発がん性試験が実施された。表18(省略)
5,000ppm投与群の雄で両側性精巣萎縮が増加したが、この所見は老齢マウスで高頻度に認められる変化であることから、毒性学的意義はないと判断された。また、同群で悪性リンパ腫の発生頻度(発生率:9.8%)が増加したが、本系統マウスに好発する背景腫瘍性病変(発生率:雄で1.45~21.7%及び雌で1.67~50.0%)であり、対照群に発生がなく、試験実施機関における雄の背景データ(発生率:12%)の範囲内であることから、検体投与による影響ではないと判断された。
本試験において、いずれの投与群にも毒性所見が認められなかったので、無毒性量は雌雄とも本試験の最高用量5,000 ppm(雄:810 mg/kg 体重/日、雌:1,080mg/kg 体重/日)であると考えられた。発がん性は認められなかった。(参照8、11)
http://www.fsc.go.jp/fsciis/evaluationDocument/show/kya0100622449b
5000ppmのグリホサートを投与したマウスの雄(摂取量としては810mg/kg体重/日)で悪性リンパ腫の発生率が9.8%であったとあります。ただし、そもそも何も投与しなくても1.45~21.7%発生することがあるがあるため、これはグリホサートの影響とはいえないという結論です。
これ以外に情報がないので、かなり安全側に立った仮定でこれをグリホサートの影響だと仮定します。
この評価書では全般にわたって遺伝毒性なしと結論づけられており、この場合は閾値を下回れば発がん性もないと判断されます。つまり、摂取量810mg/kg体重/日の1段階下の234mg/kg体重/日以下では悪性リンパ腫の増加が見られないため、影響なしとみなします。
ただし、ここでも最大限安全側に立った仮定で、曝露がゼロ以外では発がんリスクもゼロにならない、という前提で発がんリスクを計算します。
(余談) それにしても、摂取量810mg/kg体重/日というのはとてつもない量です。体重50㎏の人なら1日に40g摂取することになります。「ラウンドアップマックスロードAL 4.5L そのまま使えるタイプ」という商品があり、4.5Lで成分が0.96%ですからグリホサートとして43gです(情報源は補足参照)。これを毎日欠かさず全部飲み干すことになります。それでもなお死ぬことはなく、ようやくがんになる、ってことですからどれほど低毒性なのかよくわかります。これを散布した程度でがんになるというのもよっぽど非現実的ですね。
また、せっかくなので「疫学調査で非ホジキンリンパ腫の発生率が上昇した」ということがリスクとしてどのような意味を持つのかについても計算してみましょう。
前回に記事では、Agricultural Health Study(AHS)というコホート研究において、農業者の発がん確率を同じ地域に住む一般の発がん確率と比較したところ、非ホジキンリンパ腫の一種であるB細胞リンパ腫などで統計的有意な増加が見られたことを書きました。
これは別にグリホサートの影響というわけではありませんが、このリスクを計算してみましょう。農業者でB細胞リンパ腫が一般の人に比べて12%増加という数字を使います。
グリホサートの発がんリスクの計算
マウスの実験結果から、810mg/kg体重/日(体重50kgの人の場合40000mg/人/日)で、悪性リンパ腫の発生率が9.8%、計算が面倒なので10%(10万人あたり10000人)としましょう。
グリホサートの健康影響シリーズ第1回の記事で、一般消費者のグリホサートの摂取量は10ug/人/日程度であり、尿中濃度の高い人でも100ug/人/日程度であることを書きました。
多い人で100ug/人/日摂取している場合であっても、40000mg/人/日と比べると40万分の1となります。発がん確率が摂取量に比例すると仮定すると、「10万人あたり10000人」の40万分の1なので、「10万人あたり0.025人」と計算されます。
これは悪性リンパ腫の発生率なので、致死率をかけるともっと低くなります。死亡率は発生率の1/3程度なので(情報源は補足参照)、死亡リスクは「10万人あたり0.0083人」になります。
さらに、この数字は生涯にわたるリスクなので、いつものようなリスクのものさしで示すには年単位にする必要があります。ざっくりと寿命の85年で割ると「10万人あたり0.0001人」になりました。10億人に1人という計算ですね。
これは発がん確率が摂取量に比例すると仮定、すなわち線形閾値なしモデル(LNTモデル)を用いた計算なので、かなり過大な見積もりになります(この辺も次回の記事で解説する予定です)。最大限に大きめにリスクを見積もっても10億人に1人という数字なのです。
「グリホサートに発がん性あり」派の人たちもぜひこのようなリスク評価とともに議論すべきでしょう。
次に農業者の疫学調査から計算します。以下のリンク先からRiskToolsを使って悪性リンパ腫のリスクを表示させましょう(年齢構成は総数)。

悪性リンパ腫のリスクは「10万人あたり年間死者数で10.7人」です。そのうち非ホジキンリンパ腫は90%程度、B細胞リンパ腫は65%程度です(情報源は補足参照)。そしてB細胞リンパ腫が12%増加するので、
10.7×0.65×0.12 = 0.83
となります。
つまり「10万人あたり年間死者数で0.83人」がリスクの増加分となります。
ただし、全がんでは逆に9%の低下が見られます。全がんのリスクは「人口10万人あたり年間死者数で304.2人」なので、リスクの低下分は「人口10万人あたり年間死者数で27.3人」になります。
これらをまとめてリスクのものさしで表示すると以下のようになります。
| 要因 | 10万人あたり 年間死者数 |
| がん | 304.2 |
| 農業者の全がん低下 | 27.3 |
| 自殺 | 15.7 |
| 交通事故 | 3.5 |
| 農業者のB細胞リンパ腫増加 | 0.83 |
| 火事 | 0.8 |
| 落雷 | 0.0017 |
| 一般消費者のグリホサートによる悪性リンパ腫 | 0.0001 |
一般消費者に対する食品からの摂取のリスクはほぼ無視できる数字であり、農業者に対するB細胞リンパ腫のリスクは火災と同程度であることがわかります。ただし、全がんのリスク低下度合いはそれらのリスクを大きく上回っていますね。
まとめ:グリホサートの発がんリスクの大きさ
農薬の発がん性は、専門家が合意した一定のルールに沿った評価によって決まるものであり、科学的に完全な白黒がつくものではありません。発がん性あるなしの禅問答から抜け出すには、発がん性があったと仮定してそのリスクを計算することが有用です。
次回は発がんリスクの計算の歴史や理論的・制度的背景、受け入れられるリスクレベルについて解説します。グリホサートの健康影響シリーズは次回で最後になります。

補足
参考にした情報源のリンク
Amazon:ラウンドアップマックスロードAL 4.5L そのまま使えるタイプ

がん情報サービス:がん種別統計情報 悪性リンパ腫

竹田薬品工業株式会社:悪性リンパ腫とは?



コメント