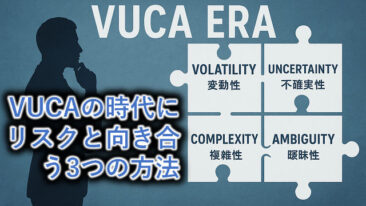 リスクガバナンス
リスクガバナンス VUCAの時代にリスクと向き合う3つの方法:リスクベース、予防ベース、熟議ベース
「VUCAの時代」とは将来の予測が困難な時代を指します。リスク学においてV, U, C, Aをそれぞれどう扱うかをまとめた論文を紹介し、「リスクベース」、「予防ベース」、「熟議ベース」という3つのアプローチによるリスクへの向き合い方を解説します。
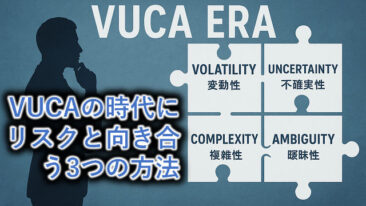 リスクガバナンス
リスクガバナンス  化学物質
化学物質  リスクガバナンス
リスクガバナンス  リスクガバナンス
リスクガバナンス  リスクガバナンス
リスクガバナンス  身近なリスク
身近なリスク  リスクガバナンス
リスクガバナンス  リスクガバナンス
リスクガバナンス  化学物質
化学物質  化学物質
化学物質