要約
食品安全の専門家とメディアの専門家がタッグを組んで、フェイクニュースへの対処法を解説した本「フェイクを見抜く」を紹介します。特に(1)ニュースが作られる裏側、(2)農薬をめぐる報道姿勢、(3)ファクトvsフェイクという対立軸の変遷に注目して紹介していきます
本文:本の紹介「フェイクを見抜く」
今回は本の紹介記事です。本ブログではフェイクニュースに関する記事をいくつか書いています。(詳細は記事最後の補足を参照してください)。そんな中、今年(2024年)になり「フェイクを見抜く」という書籍が出版されました。
唐木英明、小島正美 (2024) フェイクを見抜く 「危険」情報の読み解き方

唐木氏と小島氏による共著となります。唐木氏は現在東京大学名誉教授、食品安全情報ネットワーク(FSIN)の代表などを務めております。元は獣医学の出身で実験動物を用いた毒性評価などを専門とし、食品安全委員会などでも活動されて食品安全分野の大御所といえる存在です。最近ではAGRIFACTでも執筆されています。

一方の小島氏は元毎日新聞の記者であり、ニュースが作られる現場とその裏側について知り尽くした人です。
食品安全の専門家とメディアの専門家がタッグを組んで、フェイクニュースへの対処法を解説した本となっています。取り上げられるトピックは両氏がこれまで追いかけてきた食のリスク、農薬、遺伝子組換え作物、ワクチンなどが主になっています。
本記事ではこの本の中から、(1)ニュースが作られる裏側、(2)農薬をめぐる報道姿勢、(3)ファクトvsフェイクという対立軸の変遷などに特に注目して紹介していきましょう。
なお、本書は小島氏から恵贈いただきました。ありがとうございました。
ニュースが作られる裏側(6, 7章)
リスクの専門家としてブログを書いている私の立場からすると、本書で解説されている内容の中で科学的な解説の部分(主に唐木氏が執筆した部分)については、私が読んで新たに得る知識はほとんどありません。
逆に終盤の6, 7章あたりのなぜ偏ったニュースができあがるのか?という裏側については私にとってはなかなか面白い内容が多いです。小島氏は元新聞記者であるためマスコミの裏側のことは熟知しています。
6章に出てくる記者・メディアの5つの行動原則(p224)の内容はいつも頭に入れておきたいですね。以下のような原則がわかるとなぜ偏ったニュースができあがるのか腑に落ちます:
1.記者は弱者の立場に立つ
2.世の中に警笛を鳴らすのが記者の使命と考える
3.正義感あふれるアクションに共鳴する
4.記者は過去の誤りを訂正しない
5.記者は自説が不利になると沈黙する
この中で現在最も重要なのは3の正義に関することだと思います。これらの5つの中で矛盾することが発生した場合に最も優先される行動原則は3だと思うからです。また、SNS時代に最もバズるのは1や2ではなく3を含むコンテンツだからです。これはまた後ほど議論しましょう。
1について、小島氏が毎日新聞記者時代に村中璃子氏(HPVワクチンの危険性を否定)に取材しようとしたら市民団体からの抗議を恐れて上司からストップがかかったとの記述があります(p234)。取材を始める前にすでにスタンスが決まっている、スタンスに合わない相手には取材しない(できない)、ということは知っておくべきでしょう。
4と5も重要な項目です。過去に報道した内容と違う証拠が出てきても、過去の報道を修正せずに沈黙するだけになるようです。また、過去はなかったことにする、という態度も目立ちますね(お前がいう!?的な)。
例えば最近日本テレビのXアカウントが「雲仙普賢岳大火砕流から33年」というニュース記事をポストしたところ、日本テレビのスタッフによる行動が死者を増やした(詳細は以下の記事)というコミュニティノートがつきました。なんと日本テレビはそのポストを削除してもう一度同じ内容を投稿し(これでコミュニティノートが結果的に削除される)、さらにそれにもコミュニティノートがつくともう一度削除して3度目同じ内容を投稿したのです。これにはあきれ果てるしかありませんね。
長崎新聞:【インタビュー・上】元九州大島原地震火山観測所長 太田一也さん 「悔やまれる 人的被害」 反省残る 報道陣への遠慮 雲仙・普賢岳大火砕流30年

タクシー運転手4人を含めた報道関係の死者20人が、当時の撮影場所だった定点周辺にいた。消防団員は定点より400メートル下の北上木場農業研修所を活動拠点にしていたが、危険性の高まりから、5月29日、島原市災害対策本部を通じた私の退去要請を受けて300メートル下流の白谷公民館に退去していた。
しかし、日本テレビの取材スタッフが、住民が避難して無人となった民家の電源を無断で使用する不祥事が発覚。消防団員は6月2日、留守宅の警備も兼ね、同研修所に戻ってしまった。亡くなった警察官2人についても、報道陣らに対する避難誘導のため定点に急行。戻る途中に同研修所前で火砕流にのみ込まれた。
報道陣が避難勧告さえ守っていれば、少なくとも消防団と警察官は死なずに済んだはず。住民にも犠牲者が出たが、報道陣が避難勧告に従っていれば、危険を感じて無断入域を控えたと思う。
農薬関係(4, 5章)
この本では遺伝子組換えや農薬の話題が多く取り上げられていますが、本ブログでも多くの記事を書いている農薬について見てみましょう。特にグリホサートとネオニコチノイド系殺虫剤が取り上げられています。
グリホサート(商品名ラウンドアップ)についてはIARC(国際がん研究機関)による発がん性評価について詳しく書かれています。活動家がIARCに入り込んで発がん性ありの評価を推し進めたこと(ラウンドアップに反対する環境団体の研究員がIARCの評価パネルの委員長になった)、訴訟ビジネスをたくらんだ法律事務所もそれを後押ししたこと、などが書かれています(p141)。
Agricultural Health Study(AHS)と呼ばれる非常に信頼性の高い疫学調査では、グリホサートの使用と発がん性の間に関係が見つかりませんでした。この結果がIARCのレポートよりも先に出ていればグリホサートの発がん性は否定されたはず、という見解が本には書かれています(p142)。
ただし本ブログの過去記事でも書いたのですが、残念ながらそうはならなかっただろうと私は思います。AHSの結果よりも後に出版されたメタアナリシス論文では、AHSの結果を含めてもなおグリホサートの使用と悪性リンパ腫の一つである非ホジキンリンパ腫に有意な関係があった、とまとめられているからです。AHSの研究をほかの質の悪い研究が薄めてしまったからと考えられます。この顛末については以下の記事を参照してください。

ネオニコチノイド系殺虫剤についても長く日本で叩かれており、2021年11月に放送された「報道特集」という番組をきっかけにさらにネオニコ叩きが広まりました。以前は欧州での禁止措置の原因となったミツバチへの影響についての懸念が多かったと思いますが、最近ではワカサギの減少の原因、人の発達障害の原因などが話題となっています(p156)。
ワカサギの餌となる動物プランクトンなど水生生物への影響についても反論が試みられており、その中で農研機構によるプレスリリースが紹介されています(p169)。これは農薬による生態系へのリスクを全国的に定量化したところ、20年間で大幅に減少したことが明らかとなった、という内容です。ネオニコチノイド系殺虫剤に切り替わったことにより、むしろそれ以前よりも水生生物へのリスクは減少したのです(必読!)。
このプレスリリースは画期的な内容であったにもかかわらず、農業の業界紙などにニュースとして掲載されたのみで、一般紙にはすべて無視されたことが嘆かれています。記者たちは安全な話には興味がないらしいのです(p173)。
一連のネオニコ叩きについては、キケンだから不安情報が拡散したというよりも、「欧州で禁止されているものが日本では放置」とか「基準値が欧州よりも甘い」などの偏った情報による「日本政府はケシカラン」という政府叩きの部分が共感を得たのではないかと私は考えています。
また、記者たちは安全な話に興味がない、というよりも「安全です」というニュースでは誰も叩けないから、という解釈のほうがあてはまるのかもしれません。「危ない話選好バイアス」というよりは「正義の鉄槌選好バイアス」でしょうか?
ファクトvsフェイクという対立軸の変遷
本書のタイトルは「フェイクを見抜く」とあるとおり、基本的に○○はフェイクでファクトは△△という対立軸を扱った内容です。本書で取り扱う化学物質や遺伝子組換えは不安をあおるニュースが多く、フェイクは拡散しやすい、ということが主張されています。
ただし、最近ではファクトvsフェイクというわかりやすい対立軸ではなくなってきているようです。「○○から□□が検出された」、「□□をマウスに(大量に)曝露させると△△な影響が出た」、「今は大丈夫でも100年後にどうなるかは誰も調べていない」、などの話は全部事実であり、「ファクト」なのです。
並べていることは全部事実なのですが、そこから「□□はキケン」というニュアンスを(直接ではなく)なんとなく出してミスリードを誘うのが現代的なやり方でしょう。発信する側もそれをよくわかっているので直接的な言い方を避けるようにしています。ファクトvsフェイクという対立軸とは別のとらえ方が必要になるでしょう
SNS時代になり、情報の拡散の仕方も大きく変わってきました。システム1vsシステム2的な対立(p228)も重要ではありますが、恐怖や不安よりも怒りの感情(「○○はひどい!、ゆるせない!」など)が以前に増して重要になってきたと思います。不安になりたい人はあまりいませんが、正義の鉄槌で誰かを叩きたい人は非常に多いのです。
上記の記者の行動原則「3.正義感あふれるアクションに共鳴する」というのがこれに関係します。フェイクニュースが拡散するのは善意がベースにあります。社会のためになると思った、注意喚起になると思った、という理由でフェイクニュースを拡散していることも書かれています(p25)。
さらにはSNSを見ていると、「危険情報を重視する本能を利用して拡散する(p38)」というよりは「他人の責任を追及したい」という善vs悪の構造が強いなと感じます。農薬や遺伝子組換え、ワクチンなどは開発したメーカーやそれを認可している政府の他人の責任を追及しやすいのです。もっとリスクの大きいものがあったとしても、他人を叩けない場合は正義のアクションが盛り上がりにくいわけです。
ゼロリスク信仰(p39)、危ないと言ってくれない学者には声がかからない(p55)のような話も危険情報重視の延長と本書には書かれていますが、それもある一方で他人を叩く材料に飛びついているだけ(他人を叩けない材料には飛びつかない)という解釈もできでしょう。SNSだってものすごくリスクの高い情報ツールですが、権力を叩く絶好の武器になるのでSNS自体を叩く人はあまりいません。
学者には危ないと言ってほしいのではなく、権力を叩いてほしいのですね。そうすると大きな共感が得られます。危ないものを作ったメーカーやそれを放置した政府やは「ゆるせない!」という論調で怒りの感情を起こさせたいわけです。安全では誰も叩けません。
新型コロナウイルスに関する報道も「恐怖キャンペーン」だったと書かれていますが(p212)、実際には典型的な「悪人探し」の連続だったと思います。恐怖が支配していたのは初期のわずかな期間であり、その後は正義の鉄槌を誰に下すべきかが支配していました。
ということで、SNS時代になり拡散しやすい情報は不安・恐怖から怒りに変化し、その変化への対応を考えるべきだと感じました。これは「フェイクを見抜く」における主張とは異なりますが、本書を読んでこんなことを考えるきっかけとなってよかったと思います。
まとめ:本の紹介「フェイクを見抜く」
唐木英明・小島正美著「フェイクを見抜く」を紹介しました。ニュースが偏る原因となる記者の行動原則はいくつかありますが、SNS時代には「正義」が最も重要なキーになると考えられます。これまでのようなあからさまなフェイクは影を潜め、「ひどい」「ゆるせない」「悪に正義の鉄槌を!」という感情をあおって偏った情報を拡散することが問題になってきたと言えるでしょう。
補足
本ブログのフェイクニュース関連の過去記事を紹介しておきます。
プラットフォームがとるべき技術的対策についてのまとめ。

専門的知識のある人ほどデマの影響を過大視する第三者効果の解説

デマ発信者を黙らせようとケンカ腰や見下した態度で対応すると、信頼関係を築くというリスコミの目的から外れてしまうことを解説

科学的と合理的は異なり、個人の価値観によって合理的の意味が変わってくることを解説
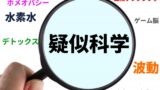
「ニセ情報に騙される人は増えたのか?」という疑問についての考察




コメント