要約
米国でメンソールたばこが禁止される方向に進んでいますが、これは単純にメンソールたばこによる健康被害があるからというよりは、健康格差の是正という新たな規制のロジックに基づいています。これはたばこ自体に手をつけずにメンソールだけを狙い撃ちするために考え出されたロジックと考えられます。
本文:メンソールたばこの禁止の新たなロジック
最近、米国においてメンソールたばこが禁止に向かうとのニュースがありました。
ロイター:米、メンソールたばこ禁止へ 当局が来年に基準案取りまとめ
人権擁護団体は、たばこ産業のマーケティング戦略が影響し、アフリカ系米国人によるメンソールたばこの利用率が白人と比べて高く、健康被害をもたらしているほか、若者の喫煙を助長しているとして、禁止を求めていた。
単純にたばこによる健康被害があるからというよりは、メンソールたばこが特にアフリカ系米国人の健康を害して全体の結構格差を助長している的な話が書いてありますね。
米国食品医薬品局(FDA)のニュースリリースの中にも同様のことが書かれています。
FDA Commits to Evidence-Based Actions Aimed at Saving Lives and Preventing Future Generations of Smokers
FDA will help significantly reduce youth initiation, increase the chances of smoking cessation among current smokers, and address health disparities experienced by communities of color, low-income populations, and LGBTQ+ individuals, all of whom are far more likely to use these tobacco products
有色人種、低所得者、LGBTQ+の人々は、これらの(メンソール入りのという意味)タバコ製品を使用する可能性が非常に高いため、これらの人々が経験する健康格差に対処することができます。
(DeepL翻訳)
なんというか、新たな時代の規制のロジックが出てきたなという感じがします。ただし、レギュラトリーサイエンスの視点では非常に興味深い点です。カナダや欧州ではすでに禁止されており、米国も少し遅れてこの流れに追随してきたのですが、なんだかモヤモヤする理由です。
たばこの健康被害はとても大きなものであり、たばこそのものに手をつけずにメンソールだけ禁止してどういう意味があるのだろうか、という感想を持ちます。メンソールだけ禁止したところで、他のたばこに移行するだけなのではないのでしょうか?このようなリスクトレードオフの話があまり出てこないように思います。
本記事では、そもそもメンソールたばこのリスクがどういうものであるのかを整理し、次にメンソールたばこ禁止がもたらすリスク低減効果を大雑把に計算してみます。最後に、なぜたばこじゃなくてメンソールだけ狙い撃ちするのか、ということについての考えを書いていきます。
たばこのリスクとメンソールたばこのリスク
まずはたばこ(メンソール添加も非添加も含む)のリスクはどの程度かをおさらいしておきます。これはすでに当ブログの過去記事にて整理してあります。
大麻は酒やたばこよりも安全か?リスク比較によって検証する

これによると、日本におけるたばこのリスクは10万人あたりの年間死者数で59.9人となります。これは2005年の数字なので、喫煙率が低下傾向にある現時点ではもう少し低いと思われますが、とりあえずこれをベースに考えます。
そしてメンソールたばこは他のたばこよりも特別に有害なものなのでしょうか?例えば以下の記事にはメンソールたばこのさまざまな有害性が書かれています。
YAHOOニュース:なぜ「メンソール・タバコ」が規制されなければならないのか
まとめると、メンソールたばこの主要な有害性としては以下の3点になります:
・メンソールを加えることでたばこを吸いやすくして喫煙者を増やす
・ニコチンとの相互作用によりニコチン依存になりやすい
・メンソールたばこは非メンソールたばこより禁煙しにくい
ただ、メンソールを添加することによる、そもそものたばこのリスクへの上乗せ分はどの程度なのか?ということは、ちょっと調べたくらいではわかりませんでした。
(参考)
Yerger (2011) Menthol’s potential effects on nicotine dependence: a tobacco industry perspective. Tobaccco Control, 20(Supple 2), ii29-ii36.

->メンソールたばこの影響についてのレビュー。吸いやすくなることとか、ニコチンとの相互作用などが記載。
Smith et al (2019) Use of Mentholated Cigarettes and Likelihood of Smoking Cessation in the United States: A Meta-Analysis. Nicotine & Tobacco Research, 22, 307-316.
->システマティックレビュー&メタアナリシスの結果。アフリカ系アメリカ人のメンソールたばこ喫煙者は、非メントソールたばこ喫煙者と比較して禁煙の確率が約12%低くなるとのこと。
メンソールたばこ禁止のリスク低減効果
そこでアプローチを変えて、メンソールたばこ禁止のリスク低減効果を計算してみます。
メンソールたばこはカナダで先行して規制されており、その後の喫煙者の行動を調べた論文から評価してみましょう。
Chung-Hall et al (2021) Evaluating the impact of menthol cigarette bans on cessation and smoking behaviours in Canada: longitudinal findings from the Canadian arm of the 2016-2018 ITC Four Country Smoking and Vaping Surveys. Tobaccco Control, 21, 1-8.

1236人の喫煙者を調査対象としており、そのうちメンソールたばこの喫煙者は138人(11.2%)でした。そして、メンソールたばこの禁止後、138人のうちの59%は非メンソールたばこに切りかえ、19.5%が引き続きメンソールたばこを使用(禁止されてないところから持ってくる?)、21.5%が禁煙したとの結果でした。
ただし、非メンソールたばこの喫煙者も14%が禁煙しており、これはメンソールの禁止とは関係のない効果と考えます。そうするとメンソール添加禁止の効果は差し引き7.5%となります。
ここからはだいぶ大雑把な計算になりますが、この7.5%がそのままリスクの減少につながると考えましょう。日本の場合で考えると、たばこによる死亡リスクとして10万人あたりの年間死者数59.9人のうち、メンソール喫煙者である11.2%(日本の数字は不明なのでカナダの数字)のさらに7.5%が減ると単純に計算し、リスク低減効果は
59.9×0.112×0.075 = 0.5
となり、10万人あたりの年間死者数で0.5人となります。リスクのものさしで表現すると以下のようになります。
| 要因 | 10万人あたり 年間死者数 |
| がん | 297 |
| たばこ | 59.9 |
| 自殺 | 15.9 |
| 交通事故 | 3.6 |
| 火事 | 0.81 |
| メンソールたばこ禁止によるリスク低減効果 | 0.5 |
| 落雷 | 0.0024 |
たばこ全体のリスクと比べてしまうと微々たる効果でしかないと言えるでしょう。それでも絶対値としてはそこそこの数字ではあるので、意味がないとまでは言えないかな、となるでしょう。
ただし、この計算はたばこをやめて別のものに手を出す、というリスクトレードオフは考慮していません。ここを考えないと本当のリスク低減効果は見えてきませんね。
今回の規制措置ではおそらく電子たばこは範囲外なので、電子たばこへの香料添加は継続するとしたら、そちらに流れる人が増えるのではないでしょうか。
もしくはメンソール禁止によってたばこはやめるけど、大麻など別のものに移行する可能性もありますね。カナダはメンソールを禁止しましたが大麻は合法化しました。過去記事にも書いたように、大麻はたばこよりもリスクは低いのでしょうけど、大麻によるリスクは10万人あたりの年間死者数で1人となっており、メンソール禁止によるリスク低減効果よりも大きくなっています。この辺のリスクトレードオフが考慮されていないように感じます。
なぜたばこ自体を禁止せずにメンソールだけ狙い撃ちなのか?
さて、ここまで書いたように、たばこ自体が非常に大きなリスクとなっているのに、なぜたばこ自体には手をつけずにメンソールだけ禁止しようとするのでしょうか?以下の記事を参考にしてみます。
YAHOOニュース:そんなに「害」があるのに「タバコ禁止」されない理由
これもざっとまとめると以下の4点になります:
1.社会が寛容
2.たばこ産業の保護(急激な変化を避ける)、たばこ税収の関係(年間2兆円ほど)
3.違法たばこの流通
4.国民の自由の保護
1について、たばこは文化の一部になっているので、リスクがあっても禁止できない、ということになります。一方でメンソールはたばこに比べると新しいもので、文化といっても若者の間に留まっていることから、禁止に持っていきやすいのでしょう。この点、最後の補足で別の例を紹介します。ただし、時代が変われば文化も変わります。たばこ自体の規制も将来的には徐々に風向きが変わっていくことでしょう。
2について、例えばコロナ禍ではんこをやめようというだけではんこ業界が大騒ぎするくらいですので、急激な変化を課すのは実行可能性が低くなるのでしょう。
3について、喫煙率の高さを考えると、覚せい剤のように取り締まるには限度があって現実的でない、ということになります。
4について、生活習慣や何を食べるかは個人の自由でもあり、どこまでそれを制限してよいかの線引きは難しいものがあります。ただし、個人の自由というのは他人に迷惑をかけない限り、という縛りが当然あります。受動喫煙の問題など明らかに他人に迷惑を掛けて健康を侵害しているので、これはやる気になればハードルにはならないでしょう。
そんなわけで、たばこ自体の禁止はハードルが高いため、そこには手をつけずにメンソールだけ禁止しようとなります。そうすると、「メンソールたばこは健康リスクがあるから」というロジックでは、「なぜたばこ自体は野放しなのか」という反論が出てくるので無理が出てくるのです。
そこで出てきたのは、「たばこの害自体というよりも健康格差をなくそう」というロジックです。冒頭にあげたのFDAのニュースリリースによると、喫煙者のうちアフリカ系米国人では85%近くがメンソールたばこを吸っていますが、白人では30%程度になります。ところが、以下のリンク先を見ると、全体の喫煙率だとアフリカ系米国人(16.8%)と非ラテン系白人(16.6%)の間ではほとんど差がありません。
これなら、たばこ自体の禁止ではなくメンソールたばこの禁止によって、アフリカ系と白人の間の健康格差が縮まるという理屈が成り立ちます。こんな感じでケースバイケースでロジックをこねながら、手をつけられそうなところから規制していく、という流れではないかというのが私の推察です。
まとめ:メンソールたばこの禁止の新たなロジック
米国でメンソールたばこが禁止される方向に進んでいますが、これは単純にメンソールたばこによる健康被害があるからというよりは、メンソールたばこがアフリカ系米国人の健康を特に害しているので、全体の健康格差の広がりを助長しているから、というロジックで説明されています。メンソールたばこ禁止によるリスク低減効果はある程度ありますが、たばこ全体のリスクに比べるとわずかな割合です。しかし、たばこ自体を規制するよりもメンソールだけを狙い撃ちする方が実行可能性のハードルが低いので、今回のような規制になったと考えられます。
補足
健康格差をどう扱うか、について3つの考え方をまとめた過去記事もぜひ参考にしてください。
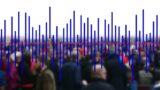
文化とリスク受容の関係については、こんにゃくゼリーと餅の関係がわかりやすいと思います。こんにゃくゼリーよりも餅の方がのどに詰まりやすいのですが、こんにゃくゼリーは規制されて餅は規制されません。こんにゃくゼリーは新しい食品なのでなくなっても困らないけど、餅は正月行事に欠かせない文化的な価値を持っているため、規制しにくいと考えられます。このように文化がからむ場合の規制の難しさについて、拙著「基準値のからくり」にまとめて1章割いています。




コメント