 身近なリスク
身近なリスク 冬のリスクその4:暑さと寒さはどっちがキケン?
能登半島地震により真冬の避難生活が続いていますが、寒い室内での生活には高い死亡リスクがあります。ただし、夏の熱中症ほどには冬の寒さのリスクはあまりニュースになりません。本記事では熱中症と低体温症のリスクを比較したり、心筋梗塞などの寒さによる間接的な死亡リスクの大きさを整理します。
 身近なリスク
身近なリスク 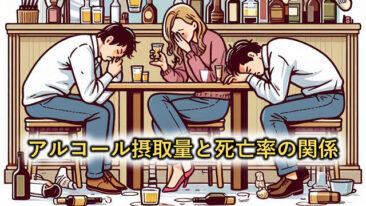 基準値問題
基準値問題  その他
その他  基準値問題
基準値問題  リスク比較
リスク比較  リスク比較
リスク比較  基準値問題
基準値問題  基準値問題
基準値問題  リスク比較
リスク比較  SNS定点観測
SNS定点観測