 リスク比較
リスク比較 日本におけるがんのリスク要因は何か?世界疾病負荷(Global Burden of Disease)研究の結果を紹介します
世界疾病負荷研究(GBD study)が提供するツールを用いて、日本のがん死亡に対するリスク要因を整理しました。その結果、たばこやお酒、不健康な食事などの日常生活に起因するがんの影響は化学物質によるがんと比べてけた違いに大きくなっています。
 リスク比較
リスク比較  化学物質
化学物質  化学物質
化学物質  化学物質
化学物質  化学物質
化学物質  身近なリスク
身近なリスク  その他
その他  身近なリスク
身近なリスク  リスクマネジメント
リスクマネジメント 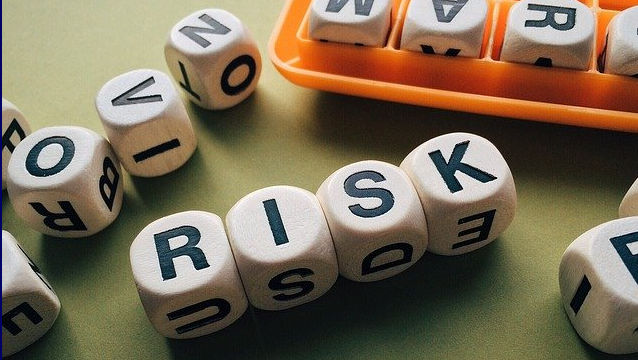 リスク比較
リスク比較