 化学物質
化学物質 マイクロプラスチック汚染の本命はタイヤ摩耗塵?~新たなハザード6-PPDキノンとの関係~
マイクロプラスチックの排出源としてのタイヤの重要性を示し、タイヤ摩耗塵の健康・環境影響について整理し、新たなハザードとしての6-PPDキノンについてまとめます。6-PPDキノンはサケに対する影響が強いことから今後要注目です。
 化学物質
化学物質  身近なリスク
身近なリスク 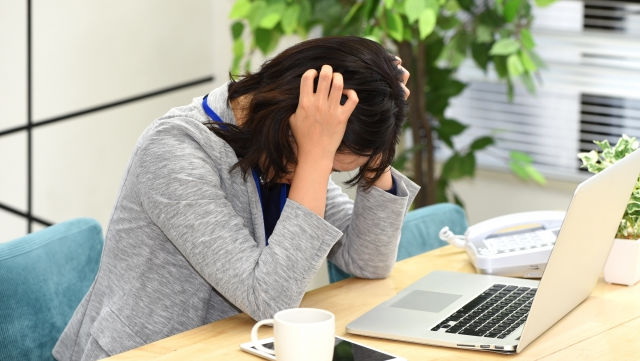 リスクマネジメント
リスクマネジメント  リスクマネジメント
リスクマネジメント  リスクマネジメント
リスクマネジメント  リスクコミュニケーション
リスクコミュニケーション  SNS定点観測
SNS定点観測  その他
その他 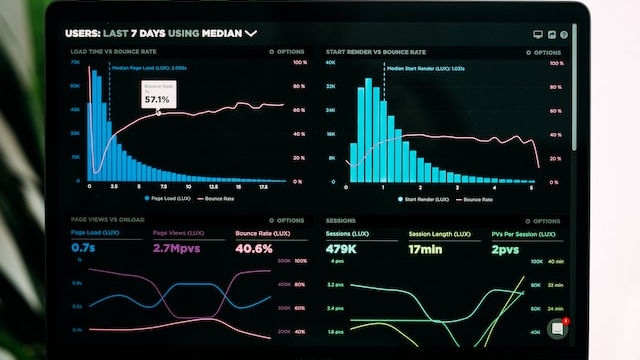 リスク比較
リスク比較  身近なリスク
身近なリスク