要約
SNSでの偽情報(デマ)に対する訂正情報そのものが悪影響を与えることがあります。2020年3月にトイレットペーパーが品薄になった際、「中国産の輸入が停止するから品薄になる」というデマに対する訂正情報がSNSで広く拡散され、その訂正情報そのものがトイレットペーパーの買い占め行動を誘発しました。
本文:偽情報(デマ)の訂正情報そのものが悪影響を与える
2025年7月20日に参議院選挙が控えており、SNSのXは普段から荒れていますが、さらに大きく荒れ模様です。私のタイムラインだと参政党はデマばかりなので投票しないように!などの発言がよく流れてきます。
ところでXでリプライや引用リプライで反論すると、さらに元の発言が広く拡散するようになるため逆効果になります。Xを運営するイーロン・マスクがXを「対戦型SNS」と公言しているように、論争になっている(リプライがたくさん付く)ポストは優先的に表示されるようになります。
このようにXのアルゴリズムを理解していないと、反論の意味がないどころかせっせと相手の主張を拡散することになるのですね。
そしてむしろ以下のように、参政党の人たちのほうがそのようなアルゴリズムをよく理解しているようにも思えます。
参政党のアンチ投稿には絶対にコメントしないでください。即ブロックでお願い致します。そういった投稿にコメントが付く事でアルゴリズムにより拡散されてしまいます。無視&ブロックで!!
逆に参政党支持者や議員の投稿にコメントしてくるアンチに対してはいっぱいコメントして下さい!(誹謗中傷NG)そうすると参政党支持者や議員の投稿がバズります!
一方、デマへの反論によって相手の主張を拡散させてしまうことのほかに、デマに対する訂正情報そのものが悪影響を与えることもあります。これはXのアルゴリズムの話ではなく、訂正情報を受け取る側の心理的な反応の話です。
本記事では、デマの訂正情報そのものが悪影響を与える事例について紹介します。まず、これまでに本ブログで書いてきたように、デマへの反論(デバンキング)は効果が小さくむしろ逆効果になることをおさらいします。次に、デマの訂正情報そのものが悪影響を与える事例として、コロナ禍でのトイレットペーパーの買い占めの話を紹介します。多くの人がXで「在庫は十分あるので買い占めないで」と発言したことでむしろ買い占めが進んでしまった事例です。最後に、このようなメカニズムが風評被害の原因にもなることについてまとめます。
デバンキング(デマへの反論)は手間のわりに効果が低い
まずはデマへの反論(デバンキング)の効果についておさらいします。
これまでのデマ対策に関する多くの研究は、デバンキングは手間がかかるわりに効果が低いことを示しています。デマの拡散スピードにデマへの反論が追い付かないためです。一方で、プレバンキング(デマが出回る前に情報の受け手側の事前訓練を行うこと)はデバンキングよりも効果が高いのではと期待されています。

デマが拡散しやすいのは感情を刺激する内容であることが多いからですね。特に怒りの感情を誘う情報は拡散しやすくなります。
選挙前になると「こんなひどいことを野放しにしている○○党は許せない!」みたいなポストがよく拡散していますね。このような傾向を利用してわざと怒りを誘う内容を投稿してインプレッションを稼ぐのが「レイジベイティング(怒りのエサをまくこと)」です。これは主張を広めたいのではなく単にインプレッションを稼ぐ(=報酬を得る)ために行われています。
こういう投稿は無視するかコミュニティノートを付けると拡散を防いでインプレッションが下がるのですが、多くの人が一生懸命反論したりすることで、ますます元の主張は拡散してインプレッションを稼がせてしまうのです。

反論して相手を黙らせなくてよいのか?と思うかもしれません。ただし、デマを一生懸命拡散させようとする人は、確信犯だったり(デマだとわかっていて広めている)、デマを強く盲信している人だったりします。強く盲信している人に反論しても、考えを改めるどころか、逆に信念を強めてしまう効果があることも知られています。これがバックファイア効果です。
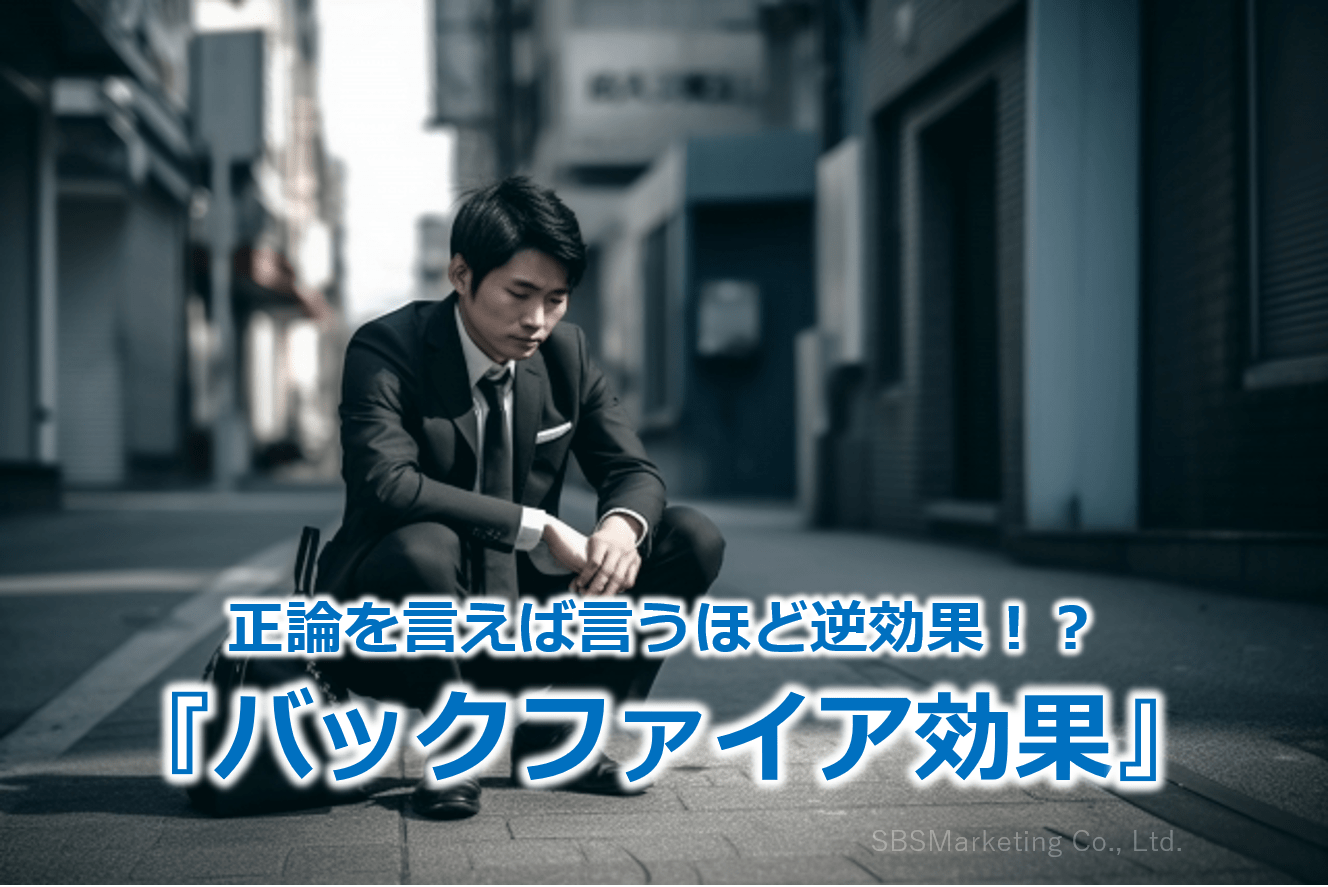
このようにユーザー同士によるデマの訂正情報はあまり効果がなく、むしろ逆効果だったりする場合もありますが、それとは別に、デマの訂正情報自体に悪影響がある、ということは案外知られていません。次にそのことについて解説します。
トイレットペーパーの買い占めの原因
2020年3月にトイレットペーパーがなくなるというデマ(中国産の輸入が停止するから、ただし実際にはトイレットペーパーはほとんどが国産)がSNSで拡散し、そのデマの訂正情報も多数拡散したものの、買い占めによって一時店頭からなくなってしまいました。この話は本ブログの過去記事にも書いています。

2020年3月ころに、トイレットペーパーがスーパーやドラッグストアの棚から消え、一時的に買えなくなりました。トイレットペーパーは中国産なので輸入が止まり品薄になる、といった情報が拡散されました。そこに、わざと買い占めてガラガラになったドラッグストアの棚の写真をつければ心理的なインパクトが非常に大きくなります。そして無くなる前に買わなきゃという人が我も我もと殺到し、品薄が現実のものとなってしまいました。買い占めたトイレットペーパーはネット上で高値で売買され、転売屋が仕掛けたものと考えられました。ただし、実際は国内で生産されており在庫がないわけではなかったため、そのうち買えるようになりました。ここで、トイレットペーパーがなくなるという予言はデマだったにも関わらず、仕掛け人の存在により実現してしまったわけです。
当時私は、予測そのものが人々の心理に影響を与えてその予測が実現してしまう、という「予言の自己成就」で買い占め行動を説明しました。ところが、デマの訂正情報そのものが影響したのでは、ということが以下の論文で報告されています。
Iizuka et al. (2022) Impact of correcting misinformation on social disruption. Plos One e0265734
総務省の調査によると、トイレットペーパーが実際に不足していると信じていた人はわずか6.2%であったとのことです。そのため、トイレットペーパーの買い占めはデマに影響されたわけではなく、デマの訂正情報の拡散によって引き起こされた可能性があるのです。
この研究において、2020年2月終わりから3月初めまでのツイートデータを収集して解析したところ、デマそのものよりも、デマの訂正情報のほうがはるかにたくさん拡散されていました。
トイレットペーパーの売上指数と、デマツイート、デマの訂正ツイートなどの相関関係を解析してモデル化したところ、最も強い影響があったのはデマの訂正ツイートでした。つまり、トイレットペーパー品薄に関するデマが広がっているという情報にのみ接触したユーザーの影響が非常に強いと考えられたのです。
この現象の理由として、自分はデマにダマされないが、他の人は簡単にデマにダマされてトイレットペーパーを買い占めてしまうだろうから、そうなる前に自分も買っておこう、と考えた人が多かったのではないか、とこの論文では考察しています。
第三者効果の影響
実際にはデマにダマされた人は少ないにもかかわらず、多くの人が「自分はダマされないが他の人は簡単にダマされる」と考えた末の行動がトイレットペーパーの売り切れをもたらした、という考察は非常に面白いですね。
この「自分はダマされないが他の人は簡単にダマされる」というバイアスは「第三者効果」と呼ばれており、本ブログの過去記事でも解説しています。

第三者効果とはマスメディアの影響に関してDavisonという社会学者が1983年に提唱した仮説です。 Davison は第二次大戦の硫黄島の戦いで日本軍がアメリカ軍の黒人兵士にバラまいたビラの効果に興味を持ったようです。そのビラには「白人のために命をかけるな」などと書かれていました。このビラは実際には黒人兵士の士気にはほとんど影響がなかったのですが、そのビラを見た白人将校たちが「黒人兵士たちはきっと影響を受けるに違いない」と考えて黒人兵士を前線から撤退させた、という話です。
「自分は(すぐデマにダマされる)一般人とは異なる賢い側の人間である」という自尊心が、デマの影響の過大視に影響するのです。
この第三者効果はリスクコミュニケーション上、いろいろなところで影響します。例えば風評被害もこの第三者効果が影響すると言われています。2011年の東日本大震災における原発事故では、福島県産の食品について流通業者が「自分は気にしないが一般の消費者は気にするだろう」と考えて、取り扱いをやめたり価格を下げるなどの対応を取ったのです(以下の論文参照)。
関谷直也 (2014) 東京電力福島第一原子力発電所事故における風評被害の課題. 農村経済研究, 32(1), 36-47
第三者効果が現れるとき、デマにダマされる人は自分とは違う種類の人間、という意識が芽生えやすくなり、これが上から目線のメッセージになったり、分断をあおることにもつながります。
じゃあどうすればよいのか?ということについてはなかなか簡単ではありません。まずはXのアルゴリズムを知って、リプライや引用リプライではなくコミュニティノートを付ける習慣をつけることが重要です。また、「デマには反論するのが最善、表立って反論しない人はデマの拡散に貢献する悪人」みたいな思い込みをやめることも重要ですね。
まとめ:偽情報(デマ)の訂正情報そのものが悪影響を与える
2020年3月にトイレットペーパーが品薄になった際、中国産の輸入が停止するから品薄になるというデマに対する訂正情報がSNSで広く拡散され、それを見た多くの人が「自分はデマにダマされないが、他の人は簡単にデマにダマされてトイレットペーパーを買い占めてしまうだろうから、そうなる前に自分も買っておこう」と考えた末の行動がトイレットペーパーの売り切れをもたらした、という事例を紹介しました。
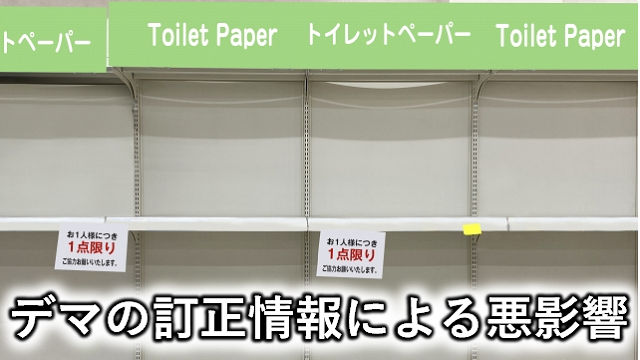


コメント