要約
一般的に自発的なリスクは非自発的なリスクよりも受容性が高いと言われていますが、自発的・非自発的なリスクという区分自体がそもそもあいまいなものであり、過剰な自己責任論を引き起こし、自発的で高いリスクを許容している現状を肯定することにもつながることについて解説します。
本文:自発的なリスクと非自発的なリスクの線引き
リスクコミュニケーションの分野では、自発的なリスクと非自発的なリスクでは受容性が違うことに注意すべき、ということが一般的に言われています。自発的なリスクのほうは受容性が高く、非自発的なリスクはその逆ということですね。
つまりは、リスクを他から押し付けられた場合には、そのリスクが低くても許容しがたい、というわけです。自分からリスクを取りに行く場合とは異なるのです。
それゆえに、死亡率などの客観的なリスクの大きさが同じくらいだったとしても、自発的なリスクと非自発的なリスクを比較したり、非自発的なリスクの大きさが小さいから許容すべき、といった論調には慎重になるべきです。
一般論としてはわかりますし、直感的にもまあそうだろうなと感じるため、あまりこの説に疑問を抱くこともないのが普通でしょう。
ただ、どこまでが自発的なリスクで、どこからが非自発的なリスクなのか?と問われるとその線引きは結構難しいのではないでしょうか?スッキリとした線引きできないとすると、これもまた安全にかかわる基準値のように「線引き問題」と言えるでしょう。
自発的なリスクとしてよく出てくる例として、タバコ(受動喫煙は除く)や自動車の運転、スキーなどがあります。この3つは鉄板の自発的なリスク(線引きに悩む必要がない)と考えられているのでしょう。特にスキーはよく出てきますね。
ただし北海道出身である私にとってのスキーは自発的な行動というよりも必須のものであり選択の余地がありません。また、北海道では自動車なしの生活は(特に冬は)不可能であるため、好んで運転するわけではありません。タバコだって依存性があるので本当に自分の意志で吸い続けているのかどうかもわかりません。
また、自発的なリスクという考え方は自己責任論と相性がよいと考えられます。タバコで健康を害した人は自分ですすんでそのリスクを取ったのだから自己責任であるため助ける必要はない、というのが過剰な自己責任論です。
さらには、リスクが小さくてベネフィットが大きいものであっても、「なんとなくイヤだから」という理由で拒否して、結果的に大きな損失をこうむったとしても、それもまた自分が選んだ結果(自発的なリスク)だからしょうがないよね、という肯定にもつながりそうです。
そのように考えるとなんだか「自発的なリスク」というもの、それから「自発的」と「非自発的」という分類、分けることの是非、がよくわからなくなってきました。
ここでは2回に分けて、自発的なリスクと非自発的なリスクについて考えてみたいと思います。ただし、あまりスッキリとした結論は出ないかもしれません。第1回の本記事では、自発的・非自発的なリスクの線引き、自発的なリスクと自己責任論の関係、自発的なリスクと非自発的なリスクの区分の是非についてまとめます。
どこまでが自発的なリスクなのか?
まず、自発的なリスクと非自発的なリスクの線引きについて考えてみたいと思います。すでに書いたとおり、自発的なリスクとしてよく出てくる例がタバコや自動車の運転、そしてスキーです。
タバコはさすがに非自発的な要素はないだろうと思われがちです。ところが、学生のときは周りがみんなタバコを吸っていて「ほらお前も吸ってみろよ!」的な場面もあります。もしくはテレビのCMやドラマなどでかっこいい俳優がタバコを吸っていて興味を持ち、ちょっと吸ってみようなどと思わされたりします。
そんな感じで周りに流されたり、TVなどの影響によって吸い始めてみると、タバコには依存性があるため、なかなかやめられなくなったりします。これって本当に自発的な行動と呼べるものなんでしょうか?自分でリスクを許容してタバコを吸っているのでしょうか?
自動車も田舎では生活必需品であり、運転したくなくても(リスクを許容していなくても)生活のために運転せざるを得ません。一方で東京で生活している人にとっては自動車の運転は必要なものではなく、車もぜいたく品でしかありません。どっちの視点で見るかによって自発的なリスクなのか非自発的なリスクなのかが変わってくるでしょう。
スキーも同様です。雪国以外の人間にとってはスキーは完全に「レジャー」であって、好んで行くものでしかありません。そうするとスキーでケガしたりすることは自発的なリスクとなるわけです。
ところが、雪国の人間にとってはスキーは冬の日常です。小さいころから靴に紐で縛り付けるプラスチックの小さいスキー板で遊んだりすることが普通で、小学校では雪が積もれば体育の授業はすべてスキーになります。やるかやらないかを選択するようなものではありません。リフトのチケットはシーズン券を持っていて、中学生になれば学校で「今日放課後ナイター(夜間に照明下で営業しているスキー場)行こうぜ」みたいな話になります(今はもうないかも)。
スキーの死亡事故は結構あります。私の周りでも死亡した例がいくつもありました。そもそも雪国ではスキー以外にも雪による事故はとても多くなります(交通事故、転倒・転落、つららの落下、除雪機による事故など)。こういう事故が自発的なリスクだと言われると、少なくとも私にとっては理解しがたい話です。
このように、よく考えてみると本当に自発的なリスクと言えるものってほとんどないように思われるのです。
自発的なリスクと自己責任論
次に、自発的なリスクという考え方は自己責任論と相性がよい、ということについて考えてみましょう。
以下の文献によれば、自己責任論とは
「当人の自律的な行為によって苦境に陥ったり他人に迷惑をかけたりした人はその責任を取らなければならない」
というものですが、これが拡大解釈されて
「本来の意味を逸脱して、実際には当人の自律的な選択によるものではない苦境であるにもかかわらず当人の責任を不当に強調する」
という過剰責任化の問題があります。
玉手慎太郎 (2018) 健康の自己責任論に対する2つの反論とその前提. 医学哲学 医学倫理, 36, 42-51
社会疫学研究者である近藤尚己は、一般向けの文章の中で次のように述べている。「健康には「本人にはどうしようもない、様々な社会的な要因」がかかわっています。病気が自業自得かどうかを線引きしたり、「自業自得度」をスコア(点数)化したりするようなことは、はなはだ困難です。判断できなければ、「自堕落な人の人工透析は10割自己負担」とするような政策を打って出ることはできません。〔…〕健康は自己責任か否か、と二元論的に考える政策議論は不毛です」
この話をリスクに置き換えても同じようなことが言えるのではないでしょうか。自業自得かどうかを線引きすることが困難であるならば、自発的・非自発的なリスクもまた線引きは困難でしょう。
さらに、自己責任論は差別や誹謗中傷にもつながりやすい特徴があります。例えば、コロナに感染した人は感染リスクが高い行動をした結果の自己責任なので、差別や誹謗中傷してもよい、という考えにつながってしまいがちです。このことは本ブログの過去記事に書いています。

この過去記事でも紹介しましたが、「自業自得の人工透析患者なんて、全員実費負担にさせよ!無理だと泣くならそのまま殺せ!今のシステムは日本を亡ぼすだけだ!!」という極論まであります。タバコによる健康被害、自動車やスキーの事故による負傷も自発的なリスクで自業自得なので実費負担すべき、みたいな話はやはりおかしいと言えるでしょう。

自発的・非自発的という区分自体がよろしくないのでは?
自発的・非自発的という区分が出てきた背景には、リスクが許容できるかどうかはリスクの大きさだけではなくそのリスクの性質が関係している、ということでした。そのリスクの性質の一つとして自発的・非自発的なリスクという区分があります。
ここから「非自発的なリスクの場合には、リスクが低いから許容すべき、という主張をすべきではない」という示唆が得られるわけです。ただし、同時に「自発的なリスクの場合、リスクが高くてもそれを許容している状況はよくない」ということに目を向ける必要があるでしょう。
また、例えば非自発的なリスク(とされるもの)で、リスクが小さくてベネフィットが大きいものがあったとします。このリスクを市民が拒否して避けることになった場合(よくあるパターン)、逆の見方をすれば大きなベネフィットを逃すという大きな損失(リスク)を市民が自発的に取った、とも言えるわけです。
このような状況を考えると、実は自発的なリスクと非自発的なリスクは表裏一体です。自発的なリスクと非自発的なリスクに分けられる、という考え方そのものがバイアスによるものなのかもしれません。
そして、このような状況(大きなリスクを自発的に取った)をそれでいいよね、と肯定してもよいのでしょうか?リスクもベネフィットも適切に見積もったうえでの選択ならよいのですが、そういう状況は現実にはあまりなさそうです。バイアスのかかった選択をそれでよし、と肯定してしまうことにも注意が必要です。
自発的・非自発的なリスクという区分自体がそもそもあいまいなものであり、そのような区分が過剰な自己責任論や差別・誹謗中傷を引き起こし、自発的で高いリスクを許容することをよしとする風潮を生み出してしまっていると考えると、自発的・非自発的という区分自体がよろしくないのでは?と考えてしまうのです。
まとめ:自発的なリスクと非自発的なリスクの線引き
一般的に自発的なリスクは非自発的なリスクよりも受容性が高いと言われており、リスクコミュニケーションの際には注意すべき点とされています。ただし、自発的・非自発的なリスクという区分自体がそもそもあいまいなものであり、自発的なリスクの結果として健康を害したりケガをした場合に自己責任だから助ける必要はない、などの過剰な自己責任論を引き起こす可能性があります。また、自発的で高いリスクを許容している現状を肯定することにもつながるため、自発的・非自発的という区分自体がよくないかもしれません。
第2回では、「自発的なリスクは非自発的なリスクよりも受容性が高い」という結果を示した古典であるスターの研究など、心理学の面からの解説をする予定です。
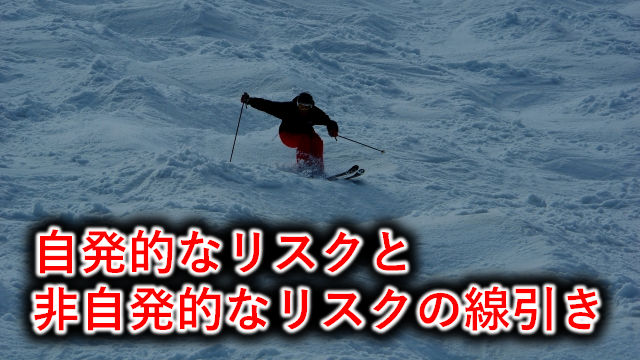


コメント