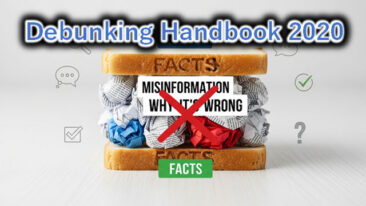 リスクコミュニケーション
リスクコミュニケーション デマ情報に対抗するための「Debunking Handbook 2020」の内容を紹介します
「Debunking Handbook 2020」の内容を紹介します。誤情報は害をもたらす可能性があり、そして誤情報はしつこい性質があるため、プレバンキングによって予防し、拡散した後は頻繁にかつ適切にデバンキングを行うことが重要です。実際の例を示しながらデバンキング情報の4つの構成要素について解説します。
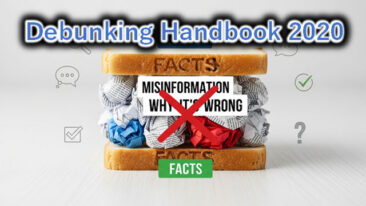 リスクコミュニケーション
リスクコミュニケーション  リスクコミュニケーション
リスクコミュニケーション  リスクコミュニケーション
リスクコミュニケーション 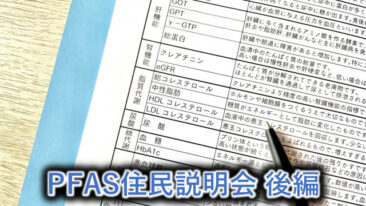 リスクコミュニケーション
リスクコミュニケーション 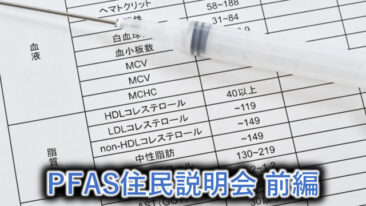 リスクコミュニケーション
リスクコミュニケーション 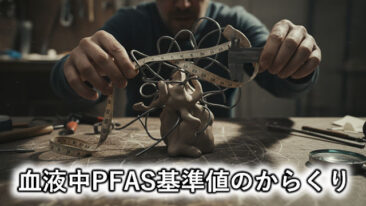 基準値問題
基準値問題  リスク比較
リスク比較  SNS定点観測
SNS定点観測  化学物質
化学物質  リスク比較
リスク比較